| 10月の絵日記へ | |||||||||
|
September23 昨日は関内のギャラリーパリへ真悟さんの個展を見に行った。NY郊外の版画工房pondside pressで制作した"モノタイプ"が中心で、ブルーのバリエーションが増え版画の紙とインクの響き合いが心地良い。"モノタイプ"とは、一つのプレス版で、1点の版画しか作れないので、絵を描くように版を作るのだと思います。 紙の材質感が暖かく優しく感じられるのは色彩が温かみのある青を使っていることもあるが、インクに油絵の具を混ぜているというその質感によるものかもしれない。真悟さんのイメージと、それを実現しようとする工房の技法研究が成果を上げているのだろう。 ゆっくりと見てから程近くの"ZAIM"で真悟さんの主宰するHatchArttとキュレイターのコアン・ジェフ・バイサさん企画による「Yokohama Boogie:Under the Influence」を見に行くと、笑顔の真悟さんが受付で迎えてくれました。 さてそこでは、かつて文明開化の「ハイカラ」な街と呼ばれた横浜の歴史的背景と、みなとみらいに見る先進性をコンセプトに、12人の国内外若手アーティストが大小一部屋づつを自由に表現の場とした(主催者によれば)グループショウなのです。 ヴィデオアートあり、部屋中に枯葉を吊るして空間を作っているもの、マネキンのような人形を天上から吊るしているもの、空気で膨らんだ巨大なビニール製の造形物、何十メートルもある和紙がコテコテに光るまで鉛筆で塗ったり描いたりしたものなど、いわゆる現代美術と呼ばれるもので、何か美大の芸術祭を見ているようでした。現代の芸術における「新しさ」とか、「先端性」とは何か考えさせられました。 この企画はアメリカ大使館、オランダ大使館、神奈川新聞社、のほか数社のラジオ局などの助成・後援を得ており、横浜市の創造芸術文化活動支援事業にもなっているので、企画としては成功と言えるのでしょう。やがて真に新しいもの、時代を切り開くものが生まれることを祈ります。  恒例「馬の写生会」は曇り空が次第に晴れて、絶好の写生日和!毎年心配なのはお天気と、参加人数と、馬が馬場にいるかどうか、この3つなのです。 恒例「馬の写生会」は曇り空が次第に晴れて、絶好の写生日和!毎年心配なのはお天気と、参加人数と、馬が馬場にいるかどうか、この3つなのです。 前日が運動会で疲れて参加できなかったりして、子供の数が少ないのは、パパママ弟君参加のファミリーで補ってくれたのでこれもクリヤー。 厩舎の前にいた小さいポニー以外の馬はもう厩舎に入ってしまって、馬場には黒い馬一頭だけ、それでもあやうくセーフなのでした。馬場にいる貴重な一頭の馬は楽しそうに駆け回ったり飛び跳ねたりしていたので、のびのびした馬の様子を見て描いた子供たちの 絵は生き生きしていました。 今回は若いお父さんお母さんの参加も多く、絵を描いている子供を見ながら過ごした時間が豊かなものであったろうと思います。  お弁当を食べてから、林の中でドングリ拾い。すぐに飽きて虫を追いかけている男の子3人組を尻目に黙々と拾う女の子達。。。それぞれが袋一杯拾ってから、芝生広場で大縄です。 はじめは怖がって中々回る縄に入れなかった1年生もだんだんコツがわかって飛べるようになるとお母さんも夢中になって応援します。付き添いの小さい弟くんたちはお父さんお母さんが抱っこして一緒に飛んだり楽しそうです。大縄はそのうち綱引きになって、少女にかえったお母さんも力いっぱい子供たちと張り合っておおはしゃぎ。ドッジボールもして最後は池に笹舟を浮かべて遊びました。  いつも森林公園に遊びに来ているファミリーも、「こんなに森林公園に長くいたの初めて」と言うほど遊びのフルコースを満喫。とっても充実した写生会でした。 いつも森林公園に遊びに来ているファミリーも、「こんなに森林公園に長くいたの初めて」と言うほど遊びのフルコースを満喫。とっても充実した写生会でした。  拾ったドングリは10月一杯かけてダンボールに貼り付けて絵や工作にします。作品は11月にGALLERY千年池で「馬の絵とどんぐり工作展」でみなさんに見ていただきます。楽しさの一杯詰まった展覧会になることでしょう。 拾ったドングリは10月一杯かけてダンボールに貼り付けて絵や工作にします。作品は11月にGALLERY千年池で「馬の絵とどんぐり工作展」でみなさんに見ていただきます。楽しさの一杯詰まった展覧会になることでしょう。 |
|||||||||
|
September11 広吉先生が講師をしている「さくら会」から武井武雄の絵本を借りて、童謡絵本の会で見ました。小さな函入りの丁寧な創りで、なんとも可愛らしいものです。手に取ると「わぁ可愛い」小さな感動が生まれます。  文字も絵も版画だったり、手書きだったり、小さな金属の棒を立ててそこに絵を映して見るものだったり、それぞれが楽しめます。 そして何よりもこんな風に創ることを楽しむことにこだわって作られたものは、必ず見る人の気持ちとつながってゆくのだということが実感されました。絵の価格も落ち、出版界も低迷していますが、本当に良いもの、創りたいものを創れば、見合う価値が生まれると思いました。 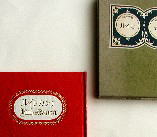 武井武雄(1894年〜1983)は長野県に生まれ、幼少時より絵を描くのが好きで、東京美術学校(現東京藝術大学)を25歳で卒業、生活を支えるためアルバイトで、「子供之友」や「日本幼年」などの子供雑誌に絵を描き始めます。幾何学的な線や、独特のデフォルメの画風は見るものを魅了します。 ある時、"子供のための絵は男子一生の仕事"と考え「童画」という言葉を生み出します。 武井武雄が活躍した1920年代というのは、西洋文化と大正デモクラシーの自由な文化が浸透しはじめだ頃で、一流の芸術家たちによる子供のための雑誌が数多く出版され、優れた童話作家や、童画家が排出された文化的に豊かな時代だったのです。 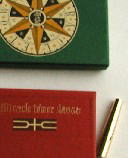 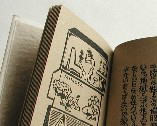 この手のひらくらいの小さな本たちはそれぞれ、古書店の1万円〜2万5000円の栞が挟んでありました。良いものはちゃんとした価格で流通していることもわかり、会のメンバーも時間はかかるけど良いものを創ろうと、確認しあったのでした。 |
|||||||||
|
September9 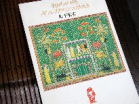 2000年に新潮社から出版した広吉先生の画集「初めの男−ギルガメシュ物語−」。最近「イシュタル」の戯曲の出版を考えているので人にさしあげる機会が増えたけれど手持ちの本が2,3冊しかなく、すでに絶版。 インターネットで全国の古書店を探したところ、山口県、岡山県、東京と3冊見つけてさっそく購入。さらに検索をすると、Yhooのオークションで一冊、これは1000円からとお買い得。もう一件はアマゾンマーケットにあり、中古価格¥20,000。「えッ ニマン円!」自分の本でも買えないよ〜。 誰かどこかでお手ごろ価格のもの見つけたらおしえてね。 |
|||||||||
|
September7  いかに雨風が強かろうとサボれないのがダンの散歩。台風9号関東地方上陸のニュースを横目で見つつ、カッパに長靴の不完全防備で森林公園へ。横殴りの雨がビシバシ当たる中、だあれもいない広々とした丘をダンが走る。これが"自由"というカタチ。心はダンになっているので、見ているだけで気持ちが晴々。。。 いつも初めに回るドーナツ公園の真ん中に立っている一本のケヤキが根っこから北東に頭を向けて倒れていたのはショックでした。HPのフレームに今月の写真として載せているあの木です。あれが最後の雄姿となってしまいました。絶対触れることなど出来なかったてっぺんの小さな枝をもらってお別れしてきました。 トチノミ、ギンナン、フウなどいろんな木の実が落ちていたので拾ってきました。ドングリは川のようにこぼれていて、山を下る時滑って危うく尻餅をつきそうになりました。23日の写生会まであるのか心配です。 アトリエの庭は柿の実、いがぐり、木の枝、葉っぱが散乱して足の踏み場もないほど。今年は豊作!と楽しみにしていたのに柿はほとんど落ちてしまいました。負けずに残った実は大きく紅くなってきっと美味しいに違いない。 |
|||||||||
|
August26 絵日記もサボりがちなこの暑い日々!!よってBBQのお知らせもメールで済ませてしまったので、ごく一部にしか届かなかったと推測されます。というか、そうなのです。ごめんなさい。以後気をつけます。 まあこじんまりと気の置けない仲間のパーティもいいもんです。 黒くシルエットになった柿の葉の間からきれいな月が見え隠れして、「こんな感じいいですね」とBBQの雰囲気をなつかしく味わっていたのは社会人2年目のサトウくん。 そうそう、社会は過酷だからたまにはグチこぼしに来なさいよ。 早めに帰ったサッチャンは月を見て、火曜日に皆既月食があるから見てください、とお知らせに戻ってきたり。。。
信頼感とか、頼れる感じがする。 大人になっても遊び心を持った人、仕事のできる人、カッコイイです。 たまには、ピースサインしてワアワアやるのもいいよね。 |
|||||||||
|
August5  夏期講習、本日のモデルはYagiちゃん。今までは描く側だったけど、今日は初モデル。白のワンピースに、白地にブルーのストライプが入ったパラソルをさして「夏」を演出、すてきです。 ダンディな熟年男性二人も初参加。シュンスケくんとyurikoちゃんがガッシュと透明水彩で美を競って、なかなかいい雰囲気で講評も楽しいです。やっぱり人物を描くのは気合がいるし、力量が試されるので、腕を衰えさせないためにOBもぜひ参加していただきたい。OBの渡辺さんも良い作品を描いていました。 講評が終わればシュークリームとドラ焼きの差し入れがあり、なごんでいました。Yagiちゃんは学校の課題作品の数々を見せてくれましたが、勉強をすることのよろこびがびんびん伝わってくるもので素晴らしいと思いました。どんどん才能が開花することでしょう、ぜひがんばってください。 |
|||||||||
| 前の絵日記へ |





